リプロンを用いた液体分子の配向の観測
1.はじめに
液体は分子の集まりです。もちろん液体中では分子はかなり自由に動き回ることができます。一方で、分子というのはたいていの場合、けっこう細長かったり偏平な形をしていたりします。すると、「分子の向き」という別の自由度を考えることができます。
この場所の移動である並進運動と、分子の向きという二つの自由度は独立なのでしょうか?
最近の研究で、実はけっこうこの二つの自由度の間には強いカップリングがあることがわかってきました。ある種の液体には、分子がみな同じ方向に並ぶという性質を示すものがあり、この分子の向きが揃ってしまっている状態を液晶と呼びます。そのため、相変化を考えるとき、通常の液体・固体などという分類ではなく、
・ 液晶相…みな向きが揃っている。
・ 等方相…向きがばらばら。
といった分類をします。
液晶という相がなぜ現れるのかまだわかっていないことも多いのですが、私たちは先に述べた「向き」と「変形」の結合がなにか一枚かんでいるのではないかとにらんでいます。
そこで等方相層から液晶が現れるそのせつなに、向きと変形の結合がどう変化するのか調べてみよう、というわけです。
この等方相の状態においては、温度によってこの向きのばらばら加減が変わります。これを配向のオーダーパラメーターQと呼び、分子の配向状態を表すときには、この値を使います。
みなきちんと揃った状態をQ=1、全くばらばらな状態をQ=0とします。液晶の配向は、磁場や電場をかければ揃います。また、先の結合の効果により、流れ場をかければ揃います。
というわけで、このような現象の測定は昔からたくさん行われてきました。分子がみな同じ方向に並んだら、複屈折が起こるであろうことはすぐ予想できます。これについては『流動複屈折』というキーワードで検索すればすぐにたくさんの論文を見つけ出すことができます。
2.リプロンとは
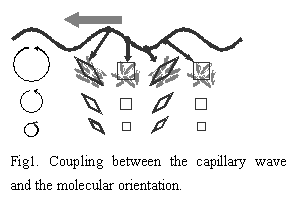 リプロンとは、液体表面に存在するさざなみのことです。マクロに見れば平らに見える液体表面もミクロに見れば、熱擾乱により、でこぼことしているわけです。どこかが盛りあがると波が伝搬します。この波は液体の粘性や弾性を反映した値の速度や寿命を持っているため、この波を光散乱で観測することによって、非接触で液体の物性を知ることができるわけです。
リプロンとは、液体表面に存在するさざなみのことです。マクロに見れば平らに見える液体表面もミクロに見れば、熱擾乱により、でこぼことしているわけです。どこかが盛りあがると波が伝搬します。この波は液体の粘性や弾性を反映した値の速度や寿命を持っているため、この波を光散乱で観測することによって、非接触で液体の物性を知ることができるわけです。
そしてこのリプロンはある点だけに着目するとただ上下に動いているのではなく、Fig.1のようにぐるりと回転していることがわかっています(最近は高校の教科書にも載っています)。つまり、液体試料でリプロンが伝搬している場合、分子の集合体は変形させられ、それにより配向を変えられていることになるわけです。
3.配向とのカップル
このぐるぐる流れ場は、波が起こったところから伝搬する方向には波の減衰につれてどんどん弱くなります。深さ方向にも同様です。この弱まりぐあいは、流体力学の計算からすぐに与えられるので、伝搬方向、および深さ方向の流動場の減衰によって、集合体の配向がどれだかバラけるか、ということが定量的に求められることになるわけです。
4.実験系
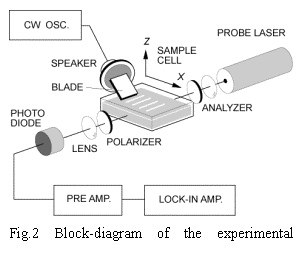 大まかには、複屈折測定に任意の波をたたせただけのシンプルなつくりになっています。
大まかには、複屈折測定に任意の波をたたせただけのシンプルなつくりになっています。
・複屈折の測定
直線偏光の光を入射させます。分子の向きが揃っていると、複屈折現象を起こして、出てきた光の偏光は楕円になっています。この楕円の太り具合により、複屈折率を知るという実験です。
・波を立たせる
オーディオスピーカーにアクリルのブレードを接着し、発振器につなげてあります。発振器によって任意の周波数で液体表面をたたきます。
5.現在までの結果
伝搬方向、深さ方向にそれぞれ測定点をずらして観測した結果が図になります。波の減衰を良くあらわした結果になりました。さらに今度は測定点を固定して、温度を変えながら観測を行っていった結果、分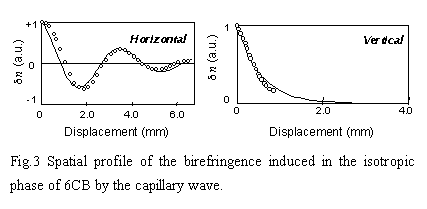 子集合体の揃い具合が『温度が低ければ低いほど揃っており、ある温度(等方相絶対不安定温度といいます)で発散する』という結果を得ることができました。
子集合体の揃い具合が『温度が低ければ低いほど揃っており、ある温度(等方相絶対不安定温度といいます)で発散する』という結果を得ることができました。
さらに、これは不思議なことですが、液体が液晶に近づくにつれ、向きと変形の結合が切れてくるらしい、ということがわかっています。ここに何か液晶相出現のヒミツが隠されているのでしょうか。